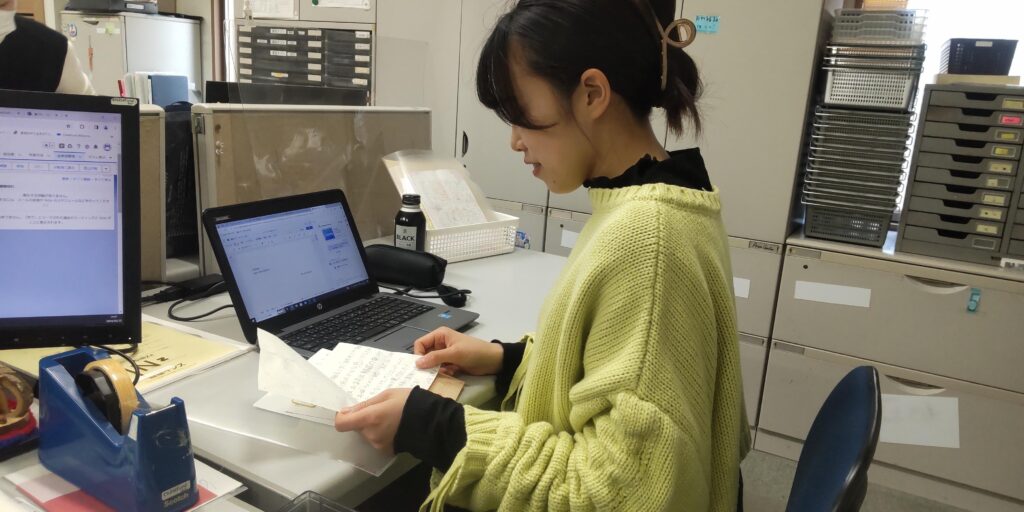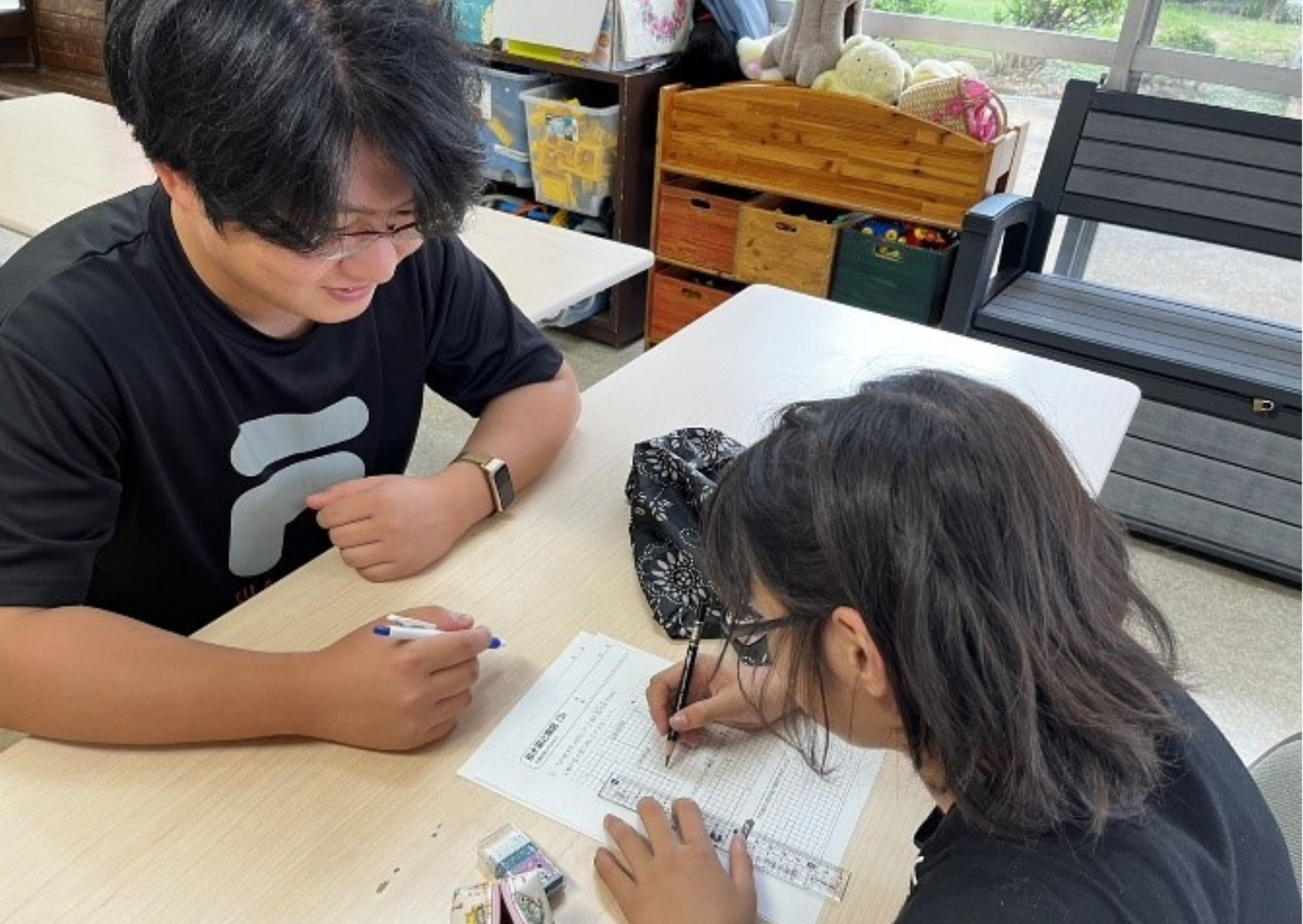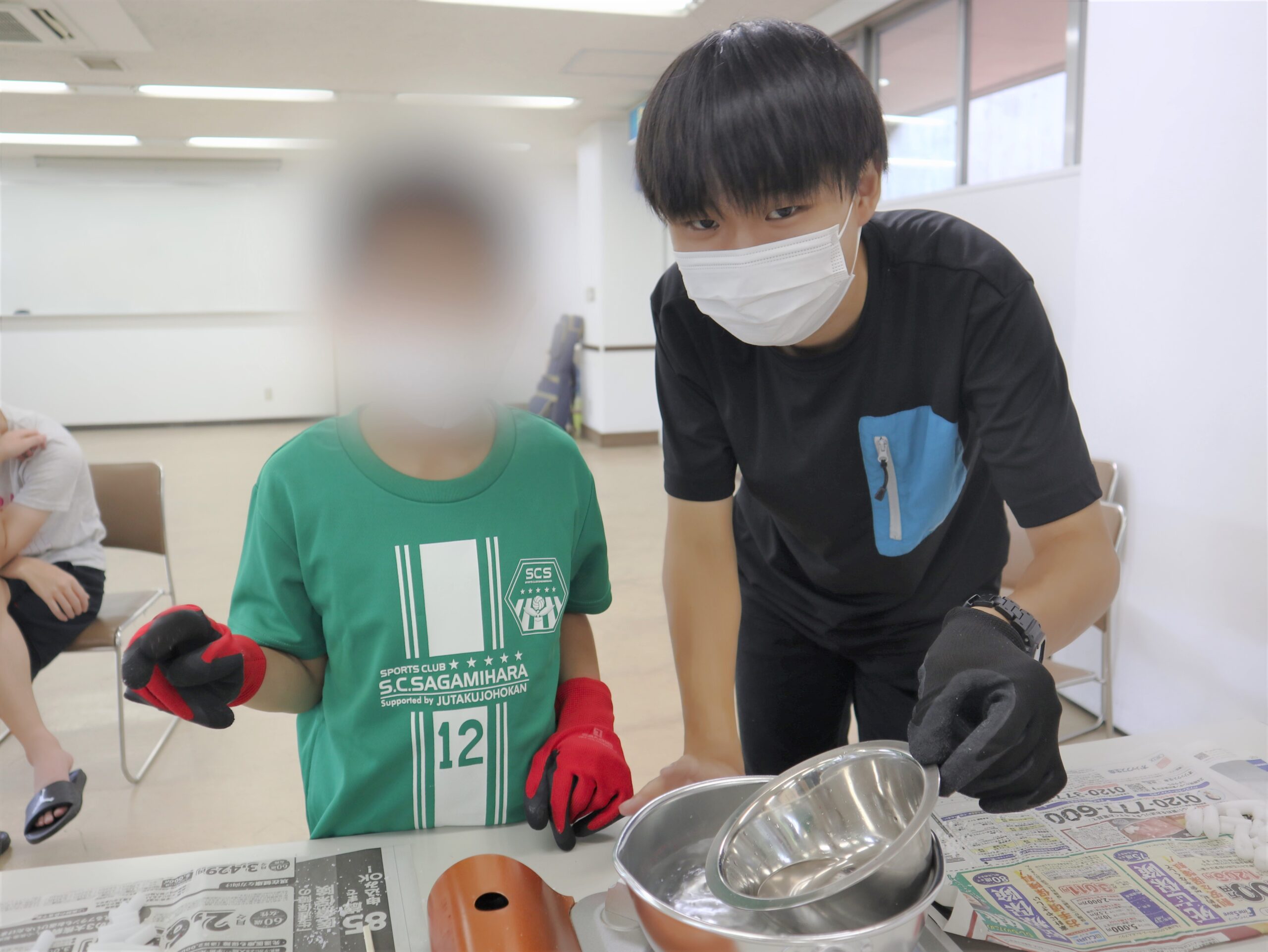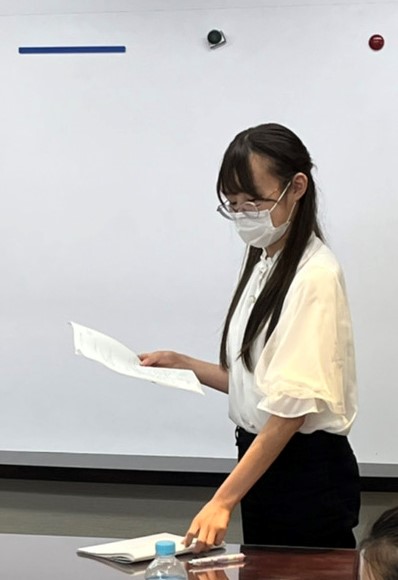インターン生紹介
インターン生紹介
インターシッププログラムを経験された方々をご紹介します。
- 福濱莉夢さん(インターン先:カナンの園、期間:2025年1月中旬~2月末)
 インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
私は大学卒業後に一般企業へ就職することが決まっていますが、将来的にはNPO団体などの活動に携わり、社会的弱者や支援を必要とされる方々に寄り添う仕事をしたいと考えています。このような目標を持つようになった背景には、大学でのキリスト教の思想に関する学びがあります。また、学内のキリスト教精神に基づくボランティアサークルに所属し、大学生活を通してさまざまな支援活動に携わってきたことも影響しています。しかし、支援を必要とされる方々と実際に向き合い、具体的な支援を行う現場での経験が不足しており、自分がどの分野に特に関心を持ち、どのように貢献できるのかについては、明確なビジョンを持てていませんでした。そのため、現場での実務経験を通じて、さらに一歩踏み込んだ具体的な支援の方法や対人支援の在り方について学びたいと考え、大学生活の学びの集大成としてこのインターンシップに申し込みました。
 インターンで携わった活動
インターンで携わった活動
1ヶ月半の中で約2週間ごとに6カ所の事業所を回らせてもらい、主に就労支援事業や生活支援事業を行う施設を中心に携わりました。多機能型事業所では、6つあるそれぞれの労働科で利用者さんと一緒に作業(薪切りや空き缶の選別など)を体験しました。外歩きや屋内運動などの健康支援活動や食事・入浴介助の支援も行い、盛岡のイオンモールで行われたアール・ブリュット展(障がいのある人たちの絵画などの作品を展示する展覧会)にも同行しました。生産型の生活介護事業所では、利用者さんと一緒に白衣に着替え、おせんべい作りの作業に携わり、生地丸めや袋のシール貼り、袋詰めなどを行いました。また、製造業務だけでなく、地域のピアノ教室やキンパ作りなどの活動にも参加しました。就労継続支援A型事業所では、工場で利用者の方とパン製造や農産加工(ジャムや味噌作り)の業務に取り組みました。そのほか、放課後等デイサービス事業では、小学校から高校までの子どもたちと交流し、一緒にすごろくゲームやレゴ遊びなどをして楽しい時間を過ごすことができました。 インターンを通して学んだこと
インターンを通して学んだこと
障がいを持つ方との実際の関わりを通して、相手が必要とする手助けや正しい配慮を行うことが支援をする上で大切であること、本当の意味での寄り添いであることを学びました。私はこれまで障がい者との関わりをもったことがなかったため、その接し方にどこか迷いを感じていた部分がありました。しかし、実際に関わってみると、目の前の人に障がいがあるという特別な意識はなくなり、必要以上に意識せず普通に接することができるようになっていました。私たちはつい障がいを持つ人は何もできないのではないかと「できないこと」に目を向けてしまいがちですが、ここでの生活を通していつの間にか「できること」に目を向けるように変えられていました。それは、カナンの園が一人ひとりの「できること」を模索しながら接する手助けを行なっていたからだと思います。また、今回のインターンシップを通じて、支援とは単なる「助けること」ではなく、その人が持つ能力を引き出し、自立を促すものであるべきだと学びました。実際に障がいの特性に応じた接し方が求められる場面が多く、それぞれの個性や状況に応じた関わり方を考えることで、利用者さんとの信頼関係が築かれていることに気づきました。障がい者福祉分野での仕事を経験する中で、私は「隣人を愛すること」の本当の意味を再認識しました。この教えは、ただ相手に対して親切であることを意味するのではなく、相手の立場を理解し、彼らの尊厳を守り、共に歩む姿勢を大切にすることだと考えます。福祉の現場で実際に働く中で、信じる力を持って支援をすることが、相手にとって大きな力になることを学びました。福祉の仕事は、ただ相手を支援することにとどまらず、その人の人生を豊かにする手助けをすることだと思います。私たち一人ひとりが持つ愛と優しさを、困難な状況にある人々と分かち合うことができるよう、今後も共生社会の実現のために挑戦することを続けていきたいと強く思わされた経験となりました。
カナンの園について
カナンの園は岩手県にある社会福祉法人です。主に知的障がいのある方への就労支援、日中活動、生活支援などを実施しています。キリストの愛をもとに、障がい者といわれる人々を中心として、全ての人が互いに尊重しつつ助け合って生きていく社会の実現をめざしています。 - 中臺野乃花さん(インターン先:CWS Japan、期間:2024年5月~9月)
 インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
私は、大学でグローバルな課題と向き合い、どうすれば異なる背景を持った人々と多文化共生することが出来るのかを考えてきました。大学2年次には、特に難民・移民について興味を持ち、学校だけではなく、NGO/NPOのフォーラムにも参加し、知見を深めてきました。しかし、大学4年生になり、幅広い知識を得ることが出来たと実感する一方で、実際に日本国内や身近な場所で助けを求めている方々にさえ直接的なアプロ―チが出来ていないと感じるようになりました。最終学年として、この学びを生かした活動をしたいと考えていた時、ウェスレー財団のインターンシッププログラムに出会いました。インターンを探している間、常にクリスチャンとして、キリスト教精神のある団体で人に仕える奉仕がしたいという思いがあり、ぜひこのプログラムに応募したいと思いました。ウェスレー財団のインターンシッププログラムは数多くのキリスト教団体と連携しており、その中のCWS Japanが活発に難民・移民支援を行っていると感じ、ここで「実際の声」を大切にしながら働きたいと強く思いました。インターンで携わった活動
CWS Japanでは、国内事業を担当しました。主な仕事は新大久保を拠点とした多文化・多世代の居場所づくりを目的とするコミュニティカフェの運営や広報、在留外国人への日本語学習支援補佐、能登でのボランティアが挙げられます。CWS Japanは国内・国外どちらの事業も「防災」にフォーカスを当てており、日本語で情報を得ることが困難な在留外国人が災害時に取り残されないための様々な活動がなされています。例として、コミュニティカフェで行った「大久保多文化共生防災まち歩き」や「ケーススタディ(在日外国人のメンタルヘルス・防災と日本語教育)」といった活動があり、それらのサポートをしていました。防災まち歩きではルート確認やマップの作成を行い、ケーススタディでは議事録係やチラシの作成を行いました。また、日本語学習支援補佐では、「やさしい日本語」という教材を使って在留外国人との簡単な会話練習から東京都の018サポートの手続きといった日常生活でのお困りごとまで対応をしていました。そして、7月には能登の仮設住宅で「ぬくもりカフェ」を開きました。全国の教会から届いたお菓子の配布やピアノ・ハープ演奏で少しでも被害に遭われた方の心が休まるよう思いを込め活動しました。インターンを通して学んだこと
インターンでは毎度新たな発見を得、刺激を受けるばかりでした。実際に活動に関わらなければ気付くことの出来なかったことがほとんどでこれまでの学びはほんの一部の知識に過ぎないと感じました。コミュニティカフェでは難民申請者や在留外国人の相談を頻繁に受けており、仕事への悩みや生活面における精神的な負担を打ち明ける方が多く、メンタルヘルスケアの必要性がどれほど高いのかを学びました。他にも、CWS Japanから紹介を受けて参加したUNHCR主催の講演会で難民申請者の生の声を聞いたり、コミュニティカフェのケーススタディで在日外国人のメンタルヘルスについて伺ったりしたことで彼らの貴重な思いを知ることが出来たと感じています。そして、大久保地域での防災まち歩きを通して、避難所の受け入れが地域住民に限られていることや、避難者カードの多言語対応がまだまだ足りないことを知りました。防災に力を入れているCWS Japanの活動に関わらなかったら、知り得なかった事実です。これまで自分の関心として挙げていた「難民・移民」はどこか海外にばかり目が向いており、難民支援がこれほどまでに身近な問題として日本に存在していると気付けませんでした。能登支援の際も最初の方はどこか支援者として行くという思いが強かったのですが、地元の人々と会ってコミュニケーションをとることで、相手の気持ちになって考え、目線を合わせる姿勢がいかに重要かを知りました。
どのようなことでも、日常生活で当たり前となっていることを疑ってみる。それが困っている隣人を助けることに繋がっていくのだとインターンを通して学びました。CWS Japanについて
CWS Japanは国内外で災害対応・防災支援をするNPOです。2011年の東日本大震災を機に、日本での活動を開始しました。災害時に支援の手が届かず取り残される人々のいない社会の実現を目指して、国内外で活動に取り組んでいます。ウェブサイト:https://www.cwsjapan.org/
- 平川莉帆さん(インターン先:神戸聖隷福祉事業団、期間:2024年7月~8月)
 インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
福祉の視点で福祉を捉えず、キリストの愛を持って目の前のその人を愛する姿勢を学ぶためにインターンに申し込みをしました。私は大学卒業後、障害福祉分野の就労移行支援員として勤務する予定です。しかし祈りの中で決断したものの、私は福祉の学部出身ではなく、実習経験も乏しいため、福祉への進路が神様の御心に叶うものであるか不安に感じていました。そこで、ウェスレー財団斡旋のキリスト教主義に基づく社会福祉法人でのインターンを通して、実習経験を積み、クリスチャンとしてどう隣人を愛するか、どのような社会人になりたいかの答えを得たいと思い、二回目の申し込みをしました。また、時間に余裕のある学生時代のうちに、出身地の関東から離れた地で生活面でも自立した生活を送ることを期待して、住み込みのインターンを希望しました。
福祉用具体験の様子
インターンで携わった活動
1か月間で、約1週間ごとに法人の5つの施設を回りました。就労継続支援事業所が3か所、就労移行支援事業所が1か所、入所・生活介護施設が1か所です。就労継続支援事業では、受注した製品の内職作業を利用者さんと一緒に行いました。その種類はタオル加工やチラシなど多様でした。その中でも自主生産品のある事業所では、カフェでの接客やマルシェでの販売にも同行しました。就労移行支援事業では、訓練と呼ばれる内職作業に利用者と一緒に取り組み、また定着支援にも同行して就職した元利用者の方との面談を行いました。入所・生活介護施設では、主に食事介助、入浴介助の支援を行い、またレクリエーション(和太鼓やエクササイズやゲーム)を一緒にしました。インターンを通して学んだこと
収穫は大きく分けて2つあります。1つ目は、障害を大きくとらえなくなったことです。当初、私は重度障害をお持ちの方の入所施設に行ったときに、殆ど全員が車いすで、手足の欠損があったり、発語が難しい方がいたり、時に奇声があがる環境が初めてで、戸惑っていました。しかし、1か月間その施設の近くで暮らすにつれて、その環境を全く意識しなくなりました。「障害」が先行するのではなく、その人はその人そのままであると、神様に愛されている一人であると、自然にそう思えるようになったからです。2つ目に、人間の注ぐ愛の限界を示されたことです。期間中、利用者さんとの関わり方に悩み、目の前の人を一面的にしか見られない時が何度もありました。それは、私の未熟さに寄る部分だけではなくて、人間の限界なのだと思います。どれだけ人格的に優れた社会人になれたとしても、結局のところは、人間は自分の愛したい姿でしか隣人を愛することができないのです。だからこそ、自分の無力を嘆くのではなく、日々神様に養われながら神様の完全な愛を受け取る必要を身をもって知りました。神様から直接的にその人に愛が注がれるように祈ること、また私自身を通して神様の愛が示されるように御言葉を根拠に生きることが、今後さらに求められていくと実感しました。神戸聖隷福祉事業団について
神戸聖隷福祉事業団は、キリスト教精神に基づき、聖書に示された愛と奉仕の実践を通して社会福祉の向上に貢献することを理念とする社会福祉法人です。「地域とともに歩み、地域に生きる施設づくり」を目標に掲げ、社会福祉事業をはじめ、高齢者福祉施設、障害者福祉施設の運営・管理を行っています。 - 武井ハンナさん(インターン先:チャイルドファンドジャパン、期間:2024年2月~4月)

写真提供:チャイルドファンドジャパン
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
大学卒業後の進路が明確でなかったため、インターンでの経験を通して視野を広げ、自分がキリスト者としてどのように社会と関わっていくか具体的に考えたいと思ったからです。私は大学で教育学部に所属しており、子どもの教育に関わる仕事に関心がありました。大学では教育実習の機会があり、教員として子どもの教育に関わることのできる機会は多くあります。しかし教員以外の立場から子どもの教育に関わる機会はほとんどありませんでした。そんな中、ウェスレー財団のインターンシッププログラムの存在を知り、学校教育現場以外の立場から子どもの教育に関わる仕事を体験してみたいと思いこのプログラムに申し込みました。インターンで携わった活動
私はチャイルド・ファンド・ジャパンの支援者サービス課というところでインターンをしていました。支援者サービス課では主に寄付をしてくださるスポンサーさんと支援を受けるチャイルドの間をつなぐ仕事をします。私はその中でもスポンサーさんとチャイルドの手紙を発送する業務と、スポンサーさんやチャイルドの手紙を翻訳する業を担当していました。翻訳作業を通してスポンサーさんとチャイルドの交流を垣間見ることができ、心温まる経験となりました。また、他のインターン生や若手の職員の方と共に若い人に寄付に興味をもってもらうために寄付の形態をどのように工夫したらよいか考え、企画案を考えるミーティングにも参加しました。インターンを通して学んだこと
チャイルド・ファンド・ジャパンでのインターンでは子どもの貧困という課題や満足な教育が受けられない子どもたちがいるという課題に向きあう機会が多くありました。その中で私の貧困に対する理解を深めることができました。私はこれまで「貧困」という問題は食べ物や着るものがなくて生きていくことが大変な人がいるという理解に留まっていました。しかし、インターン期間中に貧困という社会課題と関わる機会が多くあったことで、貧困の根本的な問題は貧困の状態から抜け出す機会がないことだと分かりました。貧困の状態から抜け出すには、自立的で安定した収入を得ることと、社会的な立場を得ることの両方が必要です。貧困の状態にある人達に食べ物や生活の支援をするだけではそのどちらも得させることは難しいでしょう。しかし、子どもたちが教育を受けて進学することはその両方とも得ることのできる可能性があります。教育を受けて進学することで安定した職を得ることができ、その結果、社会的な地位も向上するからです。これらのことから貧困の状態から抜け出すためには、抜け出す手段としての教育と子どもたちが教育を受けられるように環境を整えたりするなどの支援が必要であると分かりました。
チャイルド・ファンド・ジャパンについて
チャイルド・ファンド・ジャパンは、1975年より、アジアを中心に貧困の中で暮らす子どもの健やかな成長、家族と地域の自立を目指した活動をしています。活動をとおして人と人とが出会い、お互いに理解を深め、つながることを大切にしています。地域開発支援、緊急・復興支援、アドボカシー(広報・啓発・提言)の活動を行い、フィリピン、ネパール、スリランカの3ヵ国を支援しています。ウェブサイト:https://www.childfund.or.jp/
- 河野泰重さん(インターン先:バット博士記念ホーム、期間:2023年8月~9月下旬)

写真提供:バット博士記念ホーム
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
去年、同じ大学の先輩がウェスレー財団のインターンシッププログラムに参加していて、キリスト教団体でインターンができると知ったことがきっかけです。私は元々学校教員を目指しており、教育実習も経験しましたが将来の進路に対する迷いがありました。そのような中で、児童養護施設での働きについて知り、興味を持つようになりました。ウェスレー財団のインターンシップ先の中には児童養護施設があったので、児童養護施設での働きがどのようなものかを経験したいと思い、今回応募してみました。インターンで携わった活動
インターンでは主に2つの働きをしていました。1つ目は学習支援です。学習支援は夏休み中なら午前中、学校がある日は平日の放課後に子どもたちの宿題を見て、分からないところを教えていました。ただ子どもたちに教えるだけではなく、子どもが勉強しやすい環境を整えたり、子どもたちがやる気を引き出す声掛けなどを考えるよう心がけました。2つ目は遊びの支援です。遊びの支援は子どもたちと一緒に遊んだりしていました。遊ぶことも大切ですが、その中で何を子ども達に学ばせるかも考えます。その他にも掃除をしたり、窓の網戸を治したりと園の環境を整えたりする働きもしていました。
写真提供:バット博士記念ホーム
インターンを通して学んだこと
インターンシップを通して学んだことは、子どもとの関わり方、特に支援についてです。子どもの支援というのは様々で、子どもに勉強を教えることも、環境を整えるのもひとつです。声かけひとつであっても支援になることを学びました。子どものことを深く理解し、その子はどんなことが課題なのか・どんなことが好きなのかを把握した上で支援方法を決定していく。これが支援のプレロセスだということも知りました。また、児童養護施設での仕事が自分に向いているのかを考えると同時に、自分自身のことを深く知る機会にもなりました。
バット博士記念ホームについて
バット博士記念ホームは、東京都町田市にある児童養護施設です。園内と併せて、地域にあるグループホーム、ファミリーホームには4~6名の子ども達が職員と共に生活を営んでいます。また、地域の子どもや家庭を支援するため、様々な地域支援サービス事業も行っており、キリスト教の隣人愛を基本とした、地域や子どもに対する多様な福祉事業を展開しています。ウェブサイト:https://bott-home.org/
- 金宣韓さん(インターン先:アジア学院、期間:2023年3月中旬~4月末)

豚の世話をする様子
(写真提供:アジア学院)インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
幼い頃から両親がボランティア活動をする姿を見て育ってきました。そのため、私もボランティア活動や国際協力事業に興味をもち、高校時代からカンボジアの子供に英語教育を提供する非営利団体に所属し、活動を続けています。大学4年生になり、就職活動をする中で、今後自分が社会人になっても学生の時と同じくボランティア活動を続けたいと思いました。そのため、国際協力事業に携わっているコミュニティーの働き方を学びたいと考えました。ウェスレー財団が提供しているインターンシッププログラムはクリスチャンベースの団体や法人と連携していて、私自身クリスチャンであるため、将来自分がなりたい姿に最も近いイメージを思い描くことができると感じました。これらの理由をきっかけにウェスレー財団のインターンシッププログラムに申し込みました。
入学式でのフルート演奏
(写真提供:アジア学院)インターンで携わった活動
アジア学院のインターンやボランティアはファーム、オフィス、キッチンの三つのセクションで仕事をします。私は、その中で主にファームとオフィスのPRチームで活動しました。アジア学院は自給自足をしているコミュニティーなので、農業をする上で必須である畑の除草、種まき、苗床作りなどをしました。それだけでなく、学生やスタッフと一緒になって収穫をしたり、鶏・ヤギ・豚の面倒をみたりしました。
PRチームでは、簡単なポストを投稿することから、自分のオリジナル投稿を企画して制作することもしました。アジア学院での1日を撮影した動画を制作する企画も担い、自分のインターンシップ経験を書いた記事もウェブサイトに投稿させていただきました。
メインの活動以外にも、朝の集会でピアノ伴奏をしたり、2023年度の入学式でピアノ伴奏とフルート演奏をする機会も与えられ、さまざまな面でアジア学院での生活を深く体験することができました。
菜の花の収穫中
(写真提供:アジア学院)インターンを通して学んだこと
ウェスレー財団を通して経験したアジア学院でのインターンシップは、私にたくさんのをくれたと感じています。アジア学院で活動をしながら得た一番の学びは食と環境への理解です。常に自然に囲まれ、種をまくことから収穫まで全サイクルを経験しました。もう一つの学びは、ダイバーシティの溢れる密なコミュニティーでの暮らし方です。ミャンマー、カメルーン、エクアドル、アメリカ、ドイツなど全世界から来日した学生とボランティアが生活をともにし、それぞれの文化・観点を学ぶことができました。一つの面白かったエピソードとしては、アフリカの国々から来た学生たちが日本の教会では踊る時間がなくて悲しいといったことがありました。このように楽しい思い出もでき、ダイバースな環境での適応能力も身につけることができました。このインターンシップ経験を通して植物・動物・人を含めたさまざまな関係において共に生きることを肌で感じることができました。ウェスレー財団のインターンシッププログラムに参加して、自分の信仰を振り返ることができたと思います。クリスチャンベースの法人がキリストを中心において働く姿を近くで見ることができました。食事への感謝も、地球にやさしい有機農業も、また、世界社会に貢献したいという想いも、全てキリストの姿を反映していると思います。これから私がクリスチャンの少ない日本社会で働くとなった時、芯を神様にもって働くことの重要さに気付かれ、この経験ができたことに感謝しています。
アジア学院について
アジア学院は途上国の農村開発に携わる人材を養成する国際機関として発足しました。その目的は、東南アジア諸国ですでに農村開発に携わっていたキリスト教会とキリスト教団体の要請に応えるとともに、宗教的背景の異なる農村指導者をも学生として招くことでした。1996年以来、国内外を問わず将来農村のコミュニティに仕えることを志す日本人も「学生」として積極的に受け入れています。ウェブサイト:https://ari.ac.jp/
- 平川莉帆さん(インターン先:早稲田奉仕園、 期間:2023年2月~3月下旬)
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ

オリエンテーションキャンプにて(写真提供:早稲田奉仕園)
このインターンシッププログラムに申し込んだのは大学2年生の秋頃で、大学生活も終わりに近づいてくるのを感じていました。しかし、私はクリスチャンとして、将来どのように仕事をしていくか、大学卒業後の明確な指針を立てられていませんでした。社会勉強のできる中期・長期でできるインターンを探している中、ウェスレー財団のインターンの紹介イベントに参加して、そこで経験者の方が素晴らしい学びを得て、成長されていることを知りました。自分自身も、ウェスレー財団がコーディネートするキリスト教の精神に基づいた団体・施設でインターンを経験することで、社会人になっても、忠実に喜ばしく神様に仕えながら生きていくヒントを得られるのではないかと思い、申し込みをしました。
インターンで携わった活動

長崎フィールドワークにて(写真提供:早稲田奉仕園)
早稲田奉仕園が複数行う事業の中でも、「学寮事業」と「活動事業」の二つに関わりました。学寮事業部では、私がインターンをしている期間で、ちょうど入寮・退寮のタイミングと重なり、主にそれらの補助業務にあたりました。留学生の向けの寮では、退寮後の部屋のチェックと、入寮前の部屋の準備、入寮時の名簿作成をしました。友愛学舎というキリスト教の精神に基づく寮では、オリエンテーションキャンプ同行したのち、卒舎式と入舎式の準備と片づけをしました。活動事業部では、長崎フィールドワークの事前ミーティング参加、長崎に現地同行、フィールドワーク後は文章の編集作業をしました。ほかにも、野宿者支援給食活動や、早稲田奉仕園の職員全体ミーティングと活動事業部定例ミーティングにも参加し、インターンでの活動は多岐にわたりました。
インターンを通して学んだこと
早稲田奉仕園は、キリスト教の精神に基づき、国際的な視野に立って社会を洞察し、他社と共に生きる人間形成の場としての働きをする団体です。早稲田奉仕園の事業は密接な人間関係が必ず付きまといますが、どんな問題がおこっても、そこにいる人を愛するという姿勢が常に貫かれていました。世間の風潮に流されることなく、社会に出ても、神様の教えにのっとりキリストの愛を具現化する、それは決して簡単なことではありませんが、2か月間の短いインターン期間でもその瞬間が何度の垣間見えたのは非常に貴重な経験でした。
また、早稲田奉仕園のプログラムに参加する中で、いかに自分が狭い世界で生きているか、社会問題に対して勉強不足かということを学びました。学生の立場にある今は、行動範囲を広げ、興味関心を突き詰めることは難しいことではないと思います。しかし、社会人になっても、衰えることのない問題意識のアンテナを張り続けるのは、余裕と熱意がなければ不可能です。ですから、無知である自分を自覚して、謙虚に勉強し続けたいと願うようになりました。これから先、クリスチャンとして困難に向き合う時でも、忍耐して誠実に祈りたいと思うようになりました。勉強する喜びと意欲を得られたことが、早稲田奉仕園でのインターンを通しての一番大きな財産です。
早稲田奉仕園について
公益財団法人 早稲田奉仕園は、創設以来、キリスト教精神に基づき、国際的な視野に立って社会を洞察し、 他者と共に生きる人間形成の場としての働きをしています。早稲田奉仕園の基となったキリスト教主義の学生寮「友愛学舎」をはじめとする「学寮事業」、学生・青年から社会人まで包括的な学習と活動の場を提供する「活動事業」、貸会議室・ホール・ギャラリーを提供する「セミナーハウス事業」を展開しています。
ウェブサイト:https://www.hoshien.or.jp/
- 宇山光さん(インターン先:バット博士記念ホーム、期間:2022年8月~9月末)
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ

写真提供:バット博士記念ホーム
私は大学で幼児保育を学んでおり、将来は子どもと関わる仕事に就きたいと考えています。子どもと関わる仕事は様々ありますが、その中でも「児童養護施設」での働きに興味がありました。児童養護施設は、親がいない子どもや、親がいても虐待されるなどして適切な養育を受けられない子どもを養育する施設です。私は大学に入ってから児童養護施設に関心を持つようになり、施設実習に参加する機会を待っていましたが、コロナ禍で延期が続いてしまい、なかなか実習に行くことができませんでした。そんな中、ウェスレー財団のインターシッププログラムの存在を知り、キリスト教精神に基づいて子どもへの支援をする「バット博士記念ホーム」でのインターンを通して実践的な学びを深めていきたいと思い、申し込みました。
インターンで携わっている活動
インターン先では主に、子どもの「学習支援」と「遊び支援」を行っています。学習支援では、子どもの学校の宿題を見たり、分からないところがあれば教えたりしています。学習支援の目的は二つあり、学校の宿題をきちんと提出できるように取り組む姿勢を支援する「宿題支援」と、その子どもの課題を見つけて克服できるよう支援する「基礎学力の向上」があります。特に8月は夏休みの宿題の支援を行いました。「遊び支援」では、子どもたちの安全に注意しながら一緒に遊びます。特にこの支援は、楽しみながら子どもと関わる場面でもあり、子どもとの関係を深める時でもあると考えています。そのため、大人が全力で楽しむことがとても重要です。この二つの活動の他に、家庭舎で食事の準備を行ったり、日曜日は教会の礼拝出席の引率などをしています。インターンを通して学んでいること

写真提供:バット博士記念ホーム
インターン中に学んだことは、子どもを支援することについてです。私は施設で「指導員」という立場に立って、子どもたちの支援をする役目を任されています。しかしインターン当初は、「支援する」ことがどのようなことか理解できておらず、子どもの出来なかったことをしてあげることが支援になると考えていました。その結果、どの場面においても子どもよりも先に動いてしまうことがありました。しかし、指導員に求められていることは、子ども一人ひとりの課題に、その子ども自身が向き合えるよう促すことでした。子どもができないことを大人が代わりにしてしまうことは、子どもにとって助けにはならず、むしろ「できないことは、誰かがしてくれる」という認識を作らせてしまい、自立には繋がりません。例えば、子どもが脱ぎっぱなしにした靴を見かけたら、早く綺麗にするために大人が片付けることはよくあると思います。しかし、子どもの自立を支援するためには「靴が出ているよ」と声を掛け、子ども自身に気づかせる必要があります。子どもたちが自立できるよう、声を掛けて気づかせたり、時には一緒に取り組んだりすることが大切であることを学びました。
バット博士記念ホームについて
バット博士記念ホームは、東京都町田市にある児童養護施設です。園内と併せて、地域にあるグループホーム、ファミリーホームには4~6名の子ども達が職員と共に生活を営んでいます。また、地域の子どもや家庭を支援するため、様々な地域支援サービス事業も行っており、キリスト教の隣人愛を基本とした、地域や子どもに対する多様な福祉事業を展開しています。
ウェブサイト:https://bott-home.org/
- M.Tさん(インターン先:日本聖書協会、期間:2022年8月~9月中旬)
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ

インターシッププログラムの経験を通して⾃分の視野を広げ、社会でどのようなことが起きているのか、解決しなければいけないことは何かを知り、私は将来どのような場所で社会問題を解決していけるかを考えるきっかけにしたいと思ったからです。また、普段の学⽣⽣活で取り組んだことのない活動をすることを通じて、私に与えられている賜物と適性を知ることができたら良いと思いました。
インターンを通して聖書を⼈々にお届けするという活動に携わらせていただくことで、聖書がどのように社会で⽣かされているのか学ぶと同時に、いろいろな教団教派の⽅がいらっしゃる環境で、共に活動していくことを学んでいけたら良いなと思っています。インターンで携わっている活動
編集部、広報部、募⾦部、出版部、視聴覚部、頒布部各部の業務に関わらせていただいています。現在(2022年8月中旬)は、広報部にて若者が聖書に親しむきっかけを持つにはどのようにしたらよいか、若い世代に聖書頒布の⽀援を知ってもらうにはどのような⼯夫ができるか考え、企画案を制作しています。編集部では、来年開催予定の聖書展に若者に⾜を運んでもらうための展⽰の⼯夫を検討するため、実際に博物館を訪れて展⽰の⼯夫を考えたり、インターネットを使って若者のニーズについて分析したりしています。
写真提供:日本聖書協会
インターンを通して学んでいること
⽇本聖書協会は、もうすぐ150周年を迎える歴史のある団体です。さまざまな教団・教派の背景をもつ⽅々が共に聖書をより多くの⼈々に届けるための働きをしています。私はこのインターンを通して⼿話訳聖書の重要性を初めて知りました。聴覚障がいのある⽅の中には、日本語を読んで理解できる方もいれば⼿話を第⼀⾔語にされている方もおり、⼿話でないと聖書が⼗分に理解できない場合があります。そのような方々にとって、⼿話訳聖書はなくてはならないものであることがわかりました。⽇本語⼿話訳聖書の翻訳は 1993 年に開始されていましたが、いまだに聖書全体の約30%ほどしか翻訳されていません。また、⼿話約聖書を出版するのは通常の聖書と⽐べて費⽤が⾼く、その費⽤を⽀える献⾦も必要になっています。聖書を読みたい時にすぐ読むことができる環境で⽣活している私にとって、⾃分が⼀番理解できる⾔語で聖書を読むことができない⽅々が⽇本にもいるという事実はとても驚きでした。聖書を好きなときに好きなだけ読むことができることの幸いを学ぶことができました。またそれと同時に、聖書を⾃由に読みたくても読むことのできない⼈たちのために⽀援をしていくことが必要であることを学びました。*手話訳聖書に関する詳細はこちら(日本聖書協会のHP)をご覧ください
日本聖書協会について
日本聖書協会は、聖書協会世界連盟(UBS)の一員として、200以上の国や地域において活動している各地の聖書協会と相互に協力し合いながら、聖書翻訳、出版、頒布、支援を主な活動として全世界の聖書普及に努めています。現在、文語訳、口語訳、新共同訳、聖書協会共同訳の4つの翻訳聖書を発行し、書籍を中心として、点字、手話、音声、電子などといった様々な聖書の出版、頒布を行っています。
ウェブサイト:https://www.bible.or.jp/
- 長根山千恵子さん(インターン先:セカンドハーベスト・ジャパン、期間:2022年4月~6月末)
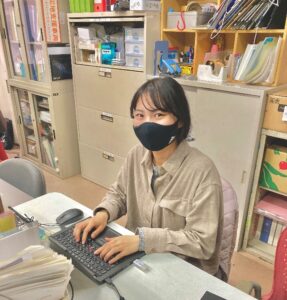
写真提供:セカンドハーベスト・ジャパン
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
私がインターンシッププログラムに申し込んだきっかけは主に2つあります。1つ目は、インターンシップの経験を通して社会課題を学び、社会に貢献したいと思ったためです。社会に存在する問題に対して、「見ないふりをせずに何かしなければならない」と思いながらも、個人では限界があることに葛藤を覚えていました。しかし、ウェスレー財団のインターンシップであれば、様々な団体の中で興味のある分野の社会課題について学ぶことができ、団体の一員として積極的に社会課題解決に関わっていけることができると思い、このプログラムに申し込みました。
2つ目は、聖書にある”Servant Leader”について学びたいと思ったためです。リーダーとして召されているならば、謙虚に「人に仕える」リーダーとして成長したいと思いながらも、どこか自己中心になってしまう自分に悩んでいました。そんな時にこの機会が与えられ、このインターンシップを通して、イエス・キリストが多くの人に仕えたように、私も人に仕えていくことを学べるのではと思い、このプログラムに参加させて頂きました。インターンで携わっている活動
セカンドハーベスト・ジャパンでは、まだ食べられるのに余ってしまった食品を、食べ物に困っている人に届けるといった活動をしています。さまざまな食品会社さんからの寄付、地域のフードドライブによって集まった食料品寄付、または個人からの寄贈品など、多くの方々からの寄付によってこの活動が成り立っています。
私がインターンをしている部署は、フードバンク部というBtoBの寄付を取り扱う部署で、企業が寄付した食品をパントリーや施設などの団体に渡しています。そのフードバンク部で、届けられた寄贈品の管理補助と、フードバンク活動を広めることを目標としたプロジェクトの一環として、ウェブサイト用のフードパントリーの地図作成に取り組んでいます。また、フードバンク部以外でも、CEOの下で「うさがみそーれープロジェクト」という沖縄で毎月食糧支援をするプロジェクトのサポートをしています。
写真提供:セカンドハーベスト・ジャパン
インターンを通して学んでいること
このインターンを通して新たに得られたことは、フードバンク活動について基本から学び、日本の貧困事情をしっかりと認識できたことです。正直に申し上げますと、活動を始めた当初は日本に貧困が存在するという事実を認識しておらず、「フードバンク」という言葉さえも聞いたことがありませんでした。ですが、スタッフの方のお話を聞いたり、パントリーや団体引き取りのお手伝いをしている中で、本当にたくさんの人が貧困に苦しみ、フードバンクを必要としていることを肌で感じています。
また、フードバンクの存在意義を再確認することもできました。当初は、フードバンクが最終的に目指しているのは「フードロスと貧困を社会からなくす」ことだと思い込んでいましたが、スタッフの方からお話を伺い、「けがをした人が病院に行くのと同じように、食に困った人がいつでも来て食品を受け取ることが出来るような『公共の財産』となること」を最終目標としていることが分かりました。このインターンシップを通して、「食のセーフティーネットを確立する」ということがいかに大切であるかを学んでいます。セカンドハーベスト・ジャパンについて
セカンドハーベスト・ジャパンは、まだ充分食べられるにも関わらずさまざまな理由で活用されない食品を受け取り、それらを必要とする方々へ提供する日本初のフードバンクです。フードバンク活動を通じて食品製造業者、食品輸入業者、食品流通業者、農業生産法人などと提携し、余剰食品を寄付することを促しています。寄付された食品は安全に保管され、全国の主要なフードバンク団体とも連携し、食品支援が必要な施設・団体・家庭(個人)などへ提供されます。
ウェブサイト:https://2hj.org/
- 五十嵐望美さん(インターン先:マイノリティ宣教センター、期間:2022年1月~3月、5月~9月中旬)

マイノリティ宣教センターの事務所にて。左が五十嵐さん (写真提供:マイノリティ宣教センター)
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
これまで平和や人権といった社会課題について関心を持ちながら学びを深めてきた中で、将来そうした経験を生かした働きができないだろうかと考えていた時に、このプログラムについて知りました。以前からキリスト教を基盤とした組織での働きを経験してみたいと思っていたので、このプログラムに申し込みました。インターンで携わっている活動
マイノリティ宣教センターが発行しているニュースレターに寄稿したり、また、センターが展開しているポッドキャストでゲストとして出演するなどといった発信活動に携わらせていただきました。また、センターが主催しているイベントの企画を考えて準備を進めたり、さまざまなプログラムにも参加しながら、センターが取り組むミッションやマイノリティの課題について学びを深めています。(五十嵐さんが出演したポッドキャストはこちらから再生できます)
インターンを通して学んでいること
センター自体の働きはまだ数年の歴史ですが(設立は2017年)、それまでにも日本のさまざまなキリスト教会が教派・宗派を超えてエキュメニカルな働きとして日本におけるマイノリティの課題に長年取り組んできた歴史的背景について知ることができました。また、センターの働きに携わっている方々とのお話を通して、マイノリティが直面している人権課題について学びを深めるだけでなく、そうした課題に対してキリスト教コミュニティがどのような役割を果たすことができるのかについて改めて考えたり見つめ直したりするようになりました。これらはすぐに答えがでるような、決して簡単な問題ではないですが、このインターンシップを通してキリスト教コミュニティだからこそ果たせるような役割の可能性や希望を感じ始めるようになりました。マイノリティ宣教センターについて
マイノリティ宣教センターは、日本においてマイノリティに対する差別と憎悪が蔓延する現状をのりこえていくために、①人種主義との闘い、②ユースプログラム、③和解と平和のスピリチュアリティ開発、④日本教会・海外教会への発信 の4つの柱のもと様々な活動をしています。これらの取り組みを軸に、この社会が多民族・多文化共生の豊かに根づく平和な社会となることをめざしています。
インターンシッププログラムに関する詳細はこちら
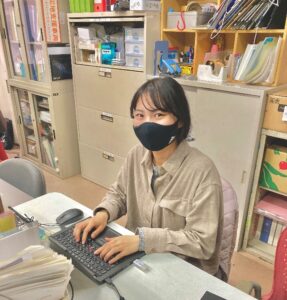 インターンシッププログラムは、国際社会で「共に生き仕えていく」次世代の人材育成を目的として、若い世代にキリスト教精神を基盤とした NGO・NPO 団体、施設、特別支援学校などでのインターンシップの機会を提供するプログラムです。
インターンシッププログラムは、国際社会で「共に生き仕えていく」次世代の人材育成を目的として、若い世代にキリスト教精神を基盤とした NGO・NPO 団体、施設、特別支援学校などでのインターンシップの機会を提供するプログラムです。

 インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ インターンで携わった活動
インターンで携わった活動 インターンを通して学んだこと
インターンを通して学んだこと インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ
インターンシッププログラムに申し込んだきっかけ